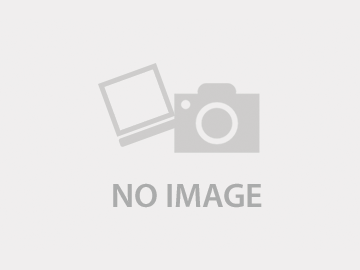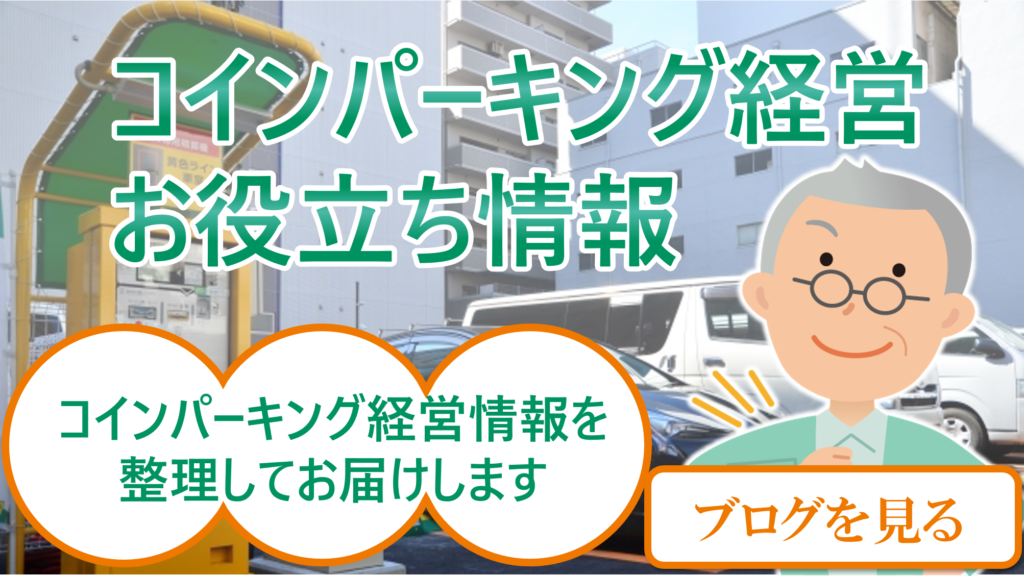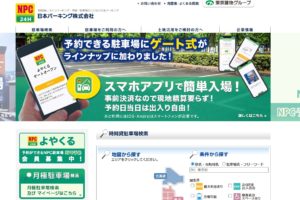駐車場経営を始めたいとお考えの方のなかには、駐車場を経営することでどのような税金が発生するのかがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
税金の種類や計算方法をあらかじめ把握することで、駐車場経営はスムーズに行えるでしょう。
そこで本記事では、駐車場経営にかかる税金の種類や計算方法、また節税対策の方法などを紹介します。
これから駐車場経営を始めたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
コインパーキング経営で確定申告が必要になる条件
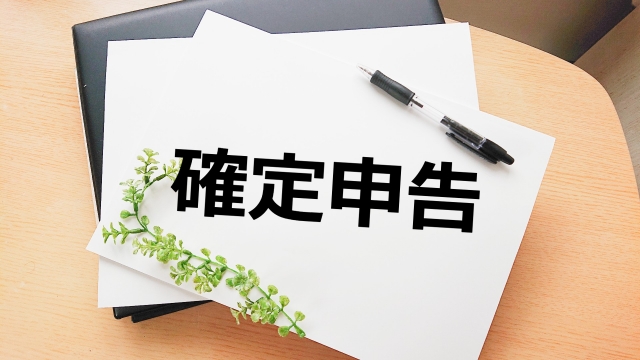
確定申告が必要になる収入基準は「年間20万円」の賃料収入です。
コインパーキング経営以外に給与収入があれば、給与と合わせて、年間20万円を超える場合に確定申告を行う必要があります。
ただし、固定資産税や運営費用などの必要経費は控除できます。
ですから、確定申告が必要なのは、給与所得とコインパーキング経営の収入を合わせた金額から「経費を差し引いた金額が20万円を超えた場合」のみです。
給与収入のない人は、その他の所得と合わせた金額から必要経費を引いて38万円を超える場合に、確定申告を行います。
確定申告の詳細については、税理士などの専門家に相談したり、国税庁のサイトを参考にしたりしてみてください。
コインパーキング経営における収入の所得の分類

月極駐車場は不動産所得に該当しますが、コインパーキングも、駐車場運営会社に一括貸しを行って固定賃料を得ているケースなら不動産所得です。
コインパーキングで駐車場運営会社に一括貸しする形式を「一括借り上げ方式」とよびます。
さらに一括借り上げ方式は、土地所有者がアスファルト舗装せずに貸す「土地貸し」と、アスファルト舗装をしたあとに貸す「施設貸し」の2種類に分類されます。
土地貸し、または施設貸しのいずれであっても不動産所得です。
一方で、コインパーキングでは、自ら駐車場を運営し、駐車場運営会社に管理だけを委託する「管理委託方式」という経営方式があります。
管理委託方式は、さらに、2種類に分かれます。
土地所有者がアスファルト舗装だけをしたあと、パーロックや自動精算機などの主要な設備を管理会社が「持ち込む方式」(賃料変動型の駐車場)がその一つです。
もう一つは、それらを土地所有者が購入する「所有方式」です。
一般的に駐車場収入は、持ち込み方式なら不動産所得、所有方式なら事業所得に分類されます。
持ち込み方式は駐車場の事業のリスクを管理会社が引き受けているため、不動産所得と判断されます。
これに対し、所有方式は駐車場の事業のリスクを土地所有者が引き受けているため、原則として事業所得の扱いです。
ただし、管理方式の所有方式であっても、例外的に雑所得に区分されることがあります。
たとえば、駐車場が1~2台しかなく、実質的に管理会社が駐車場の事業リスクをとっており、なおかつ、ほかに主要となる収入がある場合には、「雑所得」に分類されます。
駐車場経営にかかる税金の種類と計算方法

駐車場経営では、5種類の税金が発生します。
それぞれの概要と計算方法を以下にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
税金①消費税
消費税は、商品の販売やサービスの提供を行う際に発生する税金のことです。
駐車場経営において、消費税を支払う対象は駐車場の利用者であり、利用者は駐車料金と消費税の合計額を事業者に支払います。
事業者は、利用者から徴収した消費税を国に納める必要があるため、合計額から消費税を差し引いた金額が手取りとなります。
また、まっさらな土地にロープが張られているだけの「青空駐車場」の場合は、非課税取引である「土地の貸付け」に該当するため、利用者から消費税を徴収する必要がありません。
ほかにも、駐車場経営における年間の売上高が1,000万円以下の場合も、消費税の支払いは免除されます。
そのため、駐車場経営において、消費税の納税の手間を省きたいという場合は、年間の売上高が1,000万円を超えないように、経営を調整する必要があります。
消費税の計算方法
消費税は、以下の計算方法で算出できます。
「消費税=課税取引額×10%(消費税率7.8%と地方消費税率2.8%の合計)」
税金②固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの不動産の所有者に対して、市町村が課税する税金のことです。
駐車場経営は土地を活用するビジネスであるため、固定資産税の課税対象に含まれます。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、以下の計算方法で算出できます。
「固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%」
固定資産税評価額は、自治体ごとに異なります。
また、固定資産税は、物件を建てることを目的とした「住宅用地」の場合と、駐車場として利用する土地の場合で、税制上の扱いや計算方法が異なります。
住宅用家屋と駐車場の敷地が一体になっている住宅用地を活用して、駐車場経営を行う場合は、軽減措置が適用されるため、固定資産税の支払額を抑えることが可能です。
固定資産税の支払額をなるべく抑えたいという場合は、住宅用地を活用して駐車場を経営することも視野に入れましょう。
税金③都市計画税
都市計画税は、特定のエリア内の土地や建物の所有者に対して、自治体が課税する税金のことです。
具体的には、道路の建設や水道の整備が行われる「市街化区域」のエリア内が課税の対象とされています。
市街化区域のエリアは、土地が所在するエリアの自治体の都市計画課や、ホームページなどで確認できるため、駐車場経営を始める前に確認しましょう。
都市計画税の計算方法
都市計画税は、以下の計算方法で算出できます。
「都市計画税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率(~3%)」
都市計画税の税率は自治体ごとに異なり、最高で3%に設定されています。
税率は駐車場が所在する自治体に問い合わせることで確認できるため、事前に確認しましょう。
税金④相続税
相続税は、不動産や物品などの財産を相続した際に発生する税金です。
駐車場経営に利用する土地だけではなく、駐車場の経営権自体を相続した場合も、相続税の課税対象となります。
相続税の計算方法
相続税は、以下の計算方法で算出できます。
「相続税=各人の相続財産の合計額(評価額)-基礎控除額」
基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」で算出されます。
また、相続された財産の合計額(評価額)が、この基礎控除の金額を超えていない場合は、相続税は課税されません。
土地や建物などの不動産の評価額は、個人で判断することが難しいため、専門の業者に不動産の評価額の査定を依頼することをおすすめします。
別記事で、「コインパーキング経営は相続税対策になる!注意点も紹介」について詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
税金⑤所得税
所得税は、所得に対して国が課税する税金です。
所得額が多いほど税額も高くなる「累進課税制度」がとられているため、駐車場経営で得た収益が多いほど所得税は高くなります。
所得税の計算方法
所得税は、以下の計算方法で算出できます。
「所得税=課税所得金額(1年間の所得)×税率(5~45%)-税額控除」
所得税は、駐車場経営の所得額や経営の形態に応じて、税率や税金が軽減される「税額控除」という特例措置が適用されることがあります。
そのため、所得税を算出する際は、税理士や税務署に問い合わせたうえで、自身が経営している駐車場にどのような特例措置が適用されるのかを確認しましょう。
税金⑥償却資産税
固定資産税は土地と建物にかかる税金ですが、それ以外に資産を所有している場合には償却資産税がかかります。
駐車場経営におけるそれ以外の資産としては、料金精算機や車止めのためのフラップ板、舗装工事費用、外灯や看板などが対象になります。
ただしこれらの合計金額が150万円を超えない場合には免税となります。
固定資産税と違って必ずしもかかる税金ではありません。
償却資産税の計算方法
償却資産税は課税標準額×税率によって計算されます。
税率は標準税率が1.4%になっていますが、市区町村ごとに定められています。
課税標準額は取得価格と耐用年数に応じて定められた減価率で計算されます。
所有しているすべての資産評価額の合計が課税標準額となります。
なお償却資産税の免税点は150万円で非課税になりますが、申告手続きはおこなう必要があります。
税金⑦個人事業税
事業を営んでいる地域によっては個人事業税がかかります。
個人事業税は事業に対して課税される税金で、対象になるかどうかは都道府県が決めます。
そのため、営んでいる地域によって課税されることもあれば、課税されないこともあります。
また事業によって税率が異なるため、自治体から問い合わせがある場合もあります。
個人事業税の計算方法
個人事業税は(事業所得および不動産所得+所得税の事業専従者給与額-個人事業税の事業専従者給与額+青色申告特別控除-各種控除)×税率によって計算がされます。
各種控除には事業主控除で290万円、損失の繰越控除、譲渡損失の控除と繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除といったものがあります。
税率は3~5%です。個人事業税も所得よりも事業主控除のほうが多ければかからないため、必ずしも払うわけではありません。
所得税は経営方式によって異なる?

駐車場を、利用者への貸し出し期間で分類すると、コインパーキングと月極駐車場の2種類に分類けられます。
利用者への貸し出し期間でかかる税金の種類は変わりませんが、経営方式によってその金額は異なります。
まず、月極駐車場の経営で得た利益(所得)は、所得税の計算上不動産所得に区分され、これは、他の所得(サラリーマンの場合は給与所得)と合わせて課税される「総合課税」です。
これに対して、コインパーキングの経営で得た利益(所得)は、一般的に事業所得又は雑所得として区分されますが、一括借り上げ方式の場合には不動産所得になります。
駐車場の経営形態だけでなく経営方式によっても区分が異なるため、どのような種類の税金がかかるのかについては詳しく調べる必要があります。
相続税評価額
土地所有者に相続が発生した際の貸駐車場の土地の相続税評価額は、その利用形態に応じて異なります。
賃貸用建物を建てた場合や建物所有目的で貸した場合と違い、駐車場経営をしても土地の評価額は原則的に下がりません。
経営方式別の、相続税評価額は以下の表を参考になさってください、
【経営方式別】貸駐車場の土地の相続税評価額
経営方式 相続税評価額
・自主経営方式
・管理委託方式
・貸駐車場の土地の相続税評価額=自用地評価額
・貸駐車場の土地の相続税評価額自用地の評価額と同じ額
・一括借り上げ方式
・自用地評価額から賃借権価額を引いた額
(駐車場の利用者(賃借人)の費用で駐車場設備を建設することを認めるような契約の場合)
駐車場経営で節税するために押さえておきたいポイント

前項で紹介したとおり、駐車場経営を行う際は、固定資産税や所得税などさまざまな種類の税金が発生します。
「支払う税金額が多すぎて手取り額が少ない」といった事態を防ぐためには、効果的な節税対策を講じる必要があります。
駐車場経営における節税対策には以下のようなものがあるので、ぜひ参考にしてみてください。
対策①青色申告特別控除を利用する
駐車場経営で一定の条件を満たすと、最大で65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」という制度を利用して、確定申告を行うことが可能です。
青色申告特別控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
【条件】
- 駐車場経営で得た収入が雑所得以外に区分されている
- 駐車場経営で得た収入が不動産所得に区分されている場合は事業的規模である
- 電子計算のツールを利用して帳簿を作成している
確定申告を行う際は「白色申告」といわれる、少ない工数で帳簿を作成して、所得税や法人税を申告する方法が一般的です。
青色申告特別控除は節税効果が高いですが、白色申告よりも記載事項が多く、審査が厳しい傾向にあります。
日頃から取引内容を細かく記録する必要があるため、青色申告特別控除は白色申告と比較するとハードルが高いという点には注意が必要です。
そのため、青色申告特別控除を利用する場合は、普段からこまめに取引内容を記録するとともに、申請書を正確に記入することを心がけましょう。
別記事の「駐車場経営で得られた利益に対して確定申告が必要?確定申告の流れを解説」にて確定申告の基本知識や流れを詳しく解説しております。ぜひご覧ください。
対策②住宅用地を使って駐車場経営を行う
駐車場用の土地ではなく、居住を目的とした土地である「住宅用地」を使って駐車場経営を行うと、税金が軽減される特例措置が適用されます。
たとえば、200㎡までの「小規模住宅用地」を活用して駐車場を経営する場合は、課税標準価額が3分の1に、また固定資産税も6分の1まで抑えることができます。
住宅用地を使って駐車場を経営することで高い節税効果が得られるため、支払う税金をなるべく抑えたいという場合におすすめです。
ただし、どのような住宅用地でも特例措置が適用されるというわけではなく、駐車場が住宅用家屋の敷地内にあることが条件とされているため注意しましょう。
対策③特例適用要件のためのアスファルト舗装
相続税対策の一つとして、小規模宅地等の特例を活用する方法があります。
小規模宅地等の特例とは、土地の相続税評価額を減額する特例です。減額される割合は土地の用途によって変わります。
例えばアスファルト舗装された駐車場であれば貸付事業用宅地等に該当する可能性があります。
もし該当する場合には200㎡までの土地は評価額が50%減額されます。
要件としては、宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいることが求められます。
また小規模宅地等の特例が使えるかどうかの判定については個別具体的な事業によって判断されるため、アスファルト舗装をしているからといって必ず特例が受けられるわけではない点は注意しましょう。
対策④土地を建物と駐車場に利用した場合の特例活用
固定資産税には住宅用地特例があります。
これは住宅用地であれば固定資産税と都市計画税の税負担を軽減する特例です。
駐車場経営の場合もこの固定資産税の住宅用地特例が利用できる場合があります。
住宅用地特例が認められれば、敷地面積200㎡以下の小規模住宅用地であれば固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に、200㎡以上の一般住宅用地であれば固定資産税が1/3、都市計画税が2/3に軽減されます。
例えば土地と家屋を相続した場合に、あえて家屋を残して敷地の一部を活用して駐車場経営をしている場合には自宅敷地の部分は特例を使うことができます。
家屋を取り壊してその敷地すべてを駐車場としてしまうよりか固定資産税の負担を抑えることができます。
ただし、固定資産税の節税のためにわざわざ建物を建てるのはかえって建物の建築費用がかかるため、節税できる金額よりも建てる費用のほうがかかり、節税効果は見込めません。
対策⑤一括償却資産
償却資産税を節税するために利用できる制度として、一括償却資産があります。
通常10万円を超えるものを購入した場合には減価償却の処理が必要になります。
しかし減価償却の処理にも特例があります。その一つが一括償却資産での処理です。
取得価額が10万円以上20万円未満の場合、取得価額の1/3の金額を3年間にわたって減価償却費として必要経費に算入できます。
一括償却資産にした場合には、償却資産税の対象外になります。
そのため、減価償却資産を購入するときには一括償却資産で処理できる範囲のものを選んで購入するといいでしょう。
なお少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の場合には償却資産税の対象になるため、注意しましょう。
対策⑥土地をアパートとつなげる
駐車場を住宅用地と一体化させると、住宅用地の特例を受けられる可能性があります。
住宅用地には、マンションやアパートの敷地のほか、その敷地と一体利用となる庭や駐車場なども含まれます。
そのため、土地を一体化してアパートの住人用の駐車場とすることで、駐車場は住宅用地と判断されて、固定資産税の軽減措置が適用されるというわけです。
住宅用地の特例が適用されると、200㎡以内の小規模住宅用地であれば、固定資産税の6分の1が軽減されます。
固定資産税を抑えたいと考えている方は、住宅用地に駐車場を隣接させるのも一案です。
対策⑦コインパーキングの設備を総額150万円未満に抑える
駐車場経営で節税を考えるなら、フェンスやアスファルト舗装といった駐車場の設備費用にも気を払いましょう。
設備費用の総額が150万円以上の場合、固定資産税(償却資産)を支払わなければならないからです。
つまり、150万円未満に設備費用を抑えられた場合、固定資産税(償却資産)が節税できることになります。
固定資産税がかかる主な駐車設備は以下の通りです。
固定資産税がかかる駐車場設備
- フェンス
- アスファルト舗装
- コンクリート舗装
- 外灯
- 屋根
- 車止め
- 精算機
- センサー式停車機
- 防犯カメラなど
特にコインパーキングは、精算機やロック板などに設備費用がかかるため、注意が必要です。
うっかりしていると、簡単に150万円を突破してしまうおそれがあります。
設備費用が150万円を超えそうな場合は、同じ駐車場内にコインパーキングと月極駐車場を造り、駐車場の種類を分けるといった工夫も必要です。
駐車場経営が固定資産税の負担が大きくても人気の理由

なぜ駐車場経営は固定資産税の負担が大きくなるのに人気なのでしょうか。
人気の理由としては駐車場経営の始めやすさにあります。
駐車場経営を始めるためのハードルがなぜ低いのかについて具体的にみていきます。
経営方式によっては初期費用が安い
どういった経営方式でやるのかによってかかる初期費用は変わります。
例えば一括借り上げ方式であれば、土地の整地や舗装、駐車場経営に必要な設備機器への投資といった初期費用はオーナー負担でなく、企業が負担します。
一括借り上げ方式であれば、駐車場の経営状況にかかわらず土地の地代として収入を得られる点でもメリットといえます。
また管理委託方式の場合もやり方次第では初期費用を抑えて経営を始められます。
いずれにしてもアパート経営などほかの不動産投資と比較をすると初期費用を抑えて経営を始められるため、まずは駐車場経営から始めてみることができます。
狭小地や不整形地でも活用できる
狭小地や不整形地でも駐車場経営ができる点も魅力の一つです。
所有している土地が狭小地や不整形地で建物を建てるには向かない土地でも駐車場であれば駐車スペースさえ確保できれば問題なく経営ができます。
また所有していないかたでも狭小地や不整形地であれば需要がなくて周辺相場と比較して安く購入できるケースもあります。
狭小地や不整形地でもすぐ近くに人気の観光地があったり、大型の商業施設などがあったりすれば、需要は見込めます。
オフィス街などはそもそも、あまり大きな土地がない点からも狭小地や不整形地をあえて狙ってコインパーキング経営をするのも戦略の一つです。
土地の転用性が高い
もし駐車場経営が上手くいかなかった場合の事業転換もしやすいです。
建物がある場合には取り壊しが必要になります。しかも取り壊しをする前には入居者に退去してもらわなければいけません。
すんなり退去してもらえればいいですが、場合によっては立退料の支払いをしなければならず、お金もかかります。
それに比べて駐車場経営であれば、設備機器の撤去と舗装をはがせばすぐに更地にできます。
更地にしたあとに建物を建ててアパート経営をするなどほかの土地活用に転換しやすいのが駐車場経営のメリットです。
土地転用することで支払う固定資産税が変わる可能性があるため、その点は注意しましょう。
また土地転用をしなくても、その土地を売却して、次の初期費用に充てるといったこともできます。
駐車場経営を成功させるには
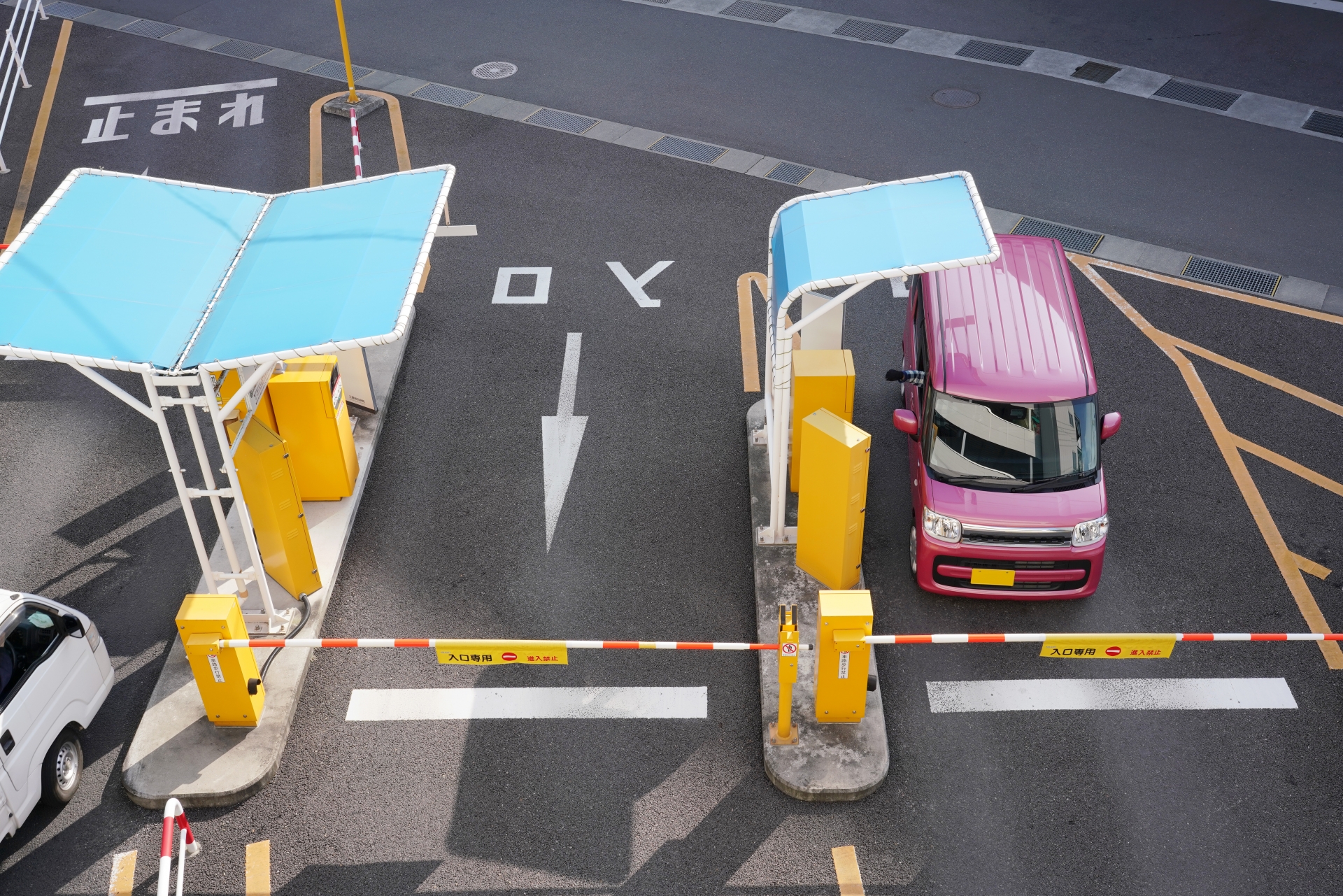
駐車場経営を成功させるためには「駐車場を利用するターゲットや人数を想定する」「適切な料金を設定する」といった、事業計画を立てることが重要です。
そのうえで、「どのくらいの税金を支払う必要があるのか」「どのような節税対策が適用できるのか」などを含め、収益のシミューレションを行うことをおすすめします。
ただし、駐車場を利用するターゲットや人数、料金の設定などは、個人で判断することが非常に難しいです。
そのため、個人で事業計画を立てることが不安な場合や、適切な料金がわからないという場合は、専門の業者に相談しましょう。
別記事で、「コインパーキング経営は委託へ!委託内容とメリット・デメリット」にてコインパーキング経営で委託できる業務内容を解説しておりますのでぜひご覧ください。
よくある質問
ここでは駐車場経営に関するよくある質問について紹介をしていきます。
Q:コインパーキングに向いている場所は?
コインパーキング経営が向いている土地は車の出入りが多い土地です。
例えば繁華街やオフィス街、観光地や大型商業施設の近くが需要を見込めます。
観光地や大型商業施設にももちろん駐車場はありますが、満車で停められないケースも多くあります。
その時に近くにコインパーキングがあれば利用されるでしょう。また観光地や商業施設は用事を済ませたあとはすぐに出るため、稼働率も高くなります。オフィス街も同じ理由です。
ただしこれらの土地は日中のにぎわっている時間の利用率は高くなりますが、夜中の利用率は低くなる傾向があります。
夜間料金を設定するといった立地にあった料金設定をするのも重要です。
Q:バイク駐車場経営は儲かる?
バイク駐車場は1台あたりに必要となる駐車場スペースが少なくて済みます。
またバイク専用の駐車場はあまり街でも見かけないため、まだ需要に対して供給が少ないといえます。
そのため、ニーズが高いところでバイク駐車場経営ができれば十分に利益を得られるでしょう。
ただ自動車よりもバイクの場合には盗難リスクが高くなるでしょうから、盗難防止対策としてロックチェーンを切られないような頑丈なものにしたり、防犯カメラを設置したりといった対策をしておくとよいでしょう。
駐車場経営をスムーズに行うためには税金の種類や節税対策を確認しましょう

いかがでしたでしょうか。
駐車場経営を行う際は、固定資産税や所得税といった、さまざまな種類の税金を支払う必要があります。
税金の種類によって税額や算出方法は異なるため、事前に確認することをおすすめします。
また、駐車場経営で利益を出すためには、効果的な節税対策を講じることも重要です。
なかでも、青色申告特別控除を利用して確定申告を行う方法や、住宅用地を使って駐車場経営を行う方法は、高い節税効果が期待できます。
本サイトでは、コインパーキング経営会社を紹介しています。
これから駐車場経営を始めたいとお考えの方は、ぜひサイトをチェックしてみてください。